受賞者・優秀作者の紹介
島田荘司選 ばらまち福山ミステリー文学新人賞では,受賞作品は協力出版社から即時出版されることになっています。
また、特別に設けられた優秀作も,随時,協力出版社から出版されています。
ここでは、今までの受賞者・優秀作者のその後の活動等を紹介します。
第13回受賞作
依存

2021年 講談社
著者よりひとこと
三年前から小説を書き始めました。 毎年、新人賞に応募を続けてきましたが全く手応えなし。挫けそうになった時、支えになったのは作品を読んで励ましてくれた身内や友人たちでした。 受賞の連絡を受けた時、真っ先に彼らの顔が浮かびました。 今回の受賞に満足せず、目標に向かってこれからも突き進んでいきたいと思います。 僕の挑戦は始まったばかり。(2021年3月)近 況
文字文化や手書き文化を広める仕事に携わるようになり、昨年から始めた書道にどっぷりはまってしまいました。「百人一首」や「奥の細道」などの古典作品を臨書していると、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
2026年に書道がユネスコの無形文化遺産として審査されるのに合わせて、筆や手書きの文化に再びスポットが当たるような企画をすることが、、当面の目標です。
そんななかで、小説と両立ができるように、時間配分を心がけなければと思っています。
まずは最終選考へ残ることを目先の目標として、このミス、清張、乱歩賞をとるまでは書き続けます。(2025年3月)
著作品一覧
依存(2021年3月 講談社)
葛藤(2021年12月 講談社)
第13回受賞作
報復の密室

2021年 講談社
千佳は生前、ミステリー賞に応募中の人物と付き合っていたという。大日方は、旧友の出版社長の協力を得て新ミステリー賞を立ち上げ、やがてその応募者の中に思わぬ人物を見出す。大日方が、学内の遺伝子組み換え実験室にその人物を呼び出そうとした時、完全な密室と化した実験室内で奇怪な第二の殺人が起こる。
著者よりひとこと
この度は、素晴らしい本格ミステリーの賞である本賞を受賞させて頂きましたこと、誠に身に余る光栄に存じます。島田先生を始め選考委員の皆様、福ミス関係者の方々、出版社の方々、そして福山市の皆様に、心よりお礼申し上げます。自分が著した本格ミステリー小説によって、多くの読者を驚かせることが私の夢でした。これから島田先生や出版社の方々のご指導を頂きながら、より良い作品を書き続けることに期待を膨らませています。(2021年3月)近 況
信州上田にて、年に長編一、二作のペースで執筆を続けています。今年は春に一作を出版する予定です。
また昨年二月から、東京都薬剤師会が発行する「都薬雑誌」という月刊誌に、隔月で連載を開始しました。この連載企画は「薬学はミステリー」という主題で、自作イラスト入り短編ミステリー小説的な読み切りエッセイを掲載するコーナーです。毒物はミステリー小説に良く出てきますが、薬物を使ったトリックを登場させるミステリー小説は意外に少ないように思います。本企画では、薬物相互作用、薬物の禁忌症、オーバードースなどを背景とした、薬物がトリックの主役となるようなショートショートを書いています。ちなみに本年二月号には、その第8回目で医薬品のボツリヌストキシン(ボトックス)を扱った「群衆にまぎれて」が掲載されています。
もう一つ私の好きな小説ジャンルが歴史ミステリーです。二〇二三年には、戦中の満州を舞台に三人のユダヤ人が連続密室殺人事件に巻き込まれる本格歴史ミステリー「ユダの密室」を出版しました。今年は、太平洋戦争末期の疎開村で起こった連続殺人事件を主題とする本格歴史ミステリー小説を出版する予定です。(2025年3月)
著作品一覧
ユダの密室(2023年3月 日本橋出版)
冒瀆のキメラ(2023年3月 アメージング出版)
薬師寺ロミの推理処方せん(2024年1月 講談社)
奇計の村(2025年4月 日本橋出版)
杏奈瑠璃亜教授の薬・毒物事件リサーチペーパー(2025年12月 アメージング出版)
第8回受賞作
アムステルダムの詭計
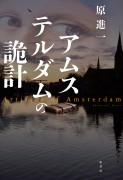
2016年4月 原書房
戦後の日本犯罪史上、最も鮮烈な印象を残したのは1968年に起きた「三億円事件」であろう。しかし、日本人だけでなく広く世界中の人々の注目を集めた点では、1965年に起きた「アムステルダム運河殺人事件」が勝っている。1965年夏、アムステルダムの運河に浮かんだ日本人死体は頭部・両脚・手首が切断され、胴体だけがトランクに詰められて発見された。当時、新進推理作家として文壇に登場した松本清張氏は本事件を小説化するに当たって綿密に取材し、被害者が替え玉であるとの説を唱えた。しかし、しばらくして自説を撤回するに至る。ヨーロッパの警察機構に加えインターポールも捜査に参画したが、事件は迷宮入りの様相を呈する。(実際に発生した事件を基にしたフィクション)
著者よりひとこと
「ばらのまち福山ミステリー文学新人賞」には、その独特な選考手法に注目していた。それは「敗者復活」のルートが用意されていたからである。選考過程が単にふるいに掛けようとするものではなく、作者の懸命さを見逃すまいとする姿勢に島田荘司先生をはじめ選者の人々の心意気が垣間見え、憧れを抱いていた。「もの書き」はスポーツ選手と同様で、試合に出場することで成長できると確信している。ピッチに立たせてもらえたことを大変光栄に思う。(2016年5月)
近 況
昨年は初孫が生まれ、六カ月になった。子供はよく動く。 私は抱っこできない。座ってミルクを飲ませることだけ許されている。孫は無条件に可愛い。おしっこをしてもあくびをしても、私の眼尻は下がりっぱなしだろう。長生きしてたら、ひょんなことから幸運に恵まれた。
私は1月下旬に一週間程度入院する。前立腺肥大のため手術を受る。全身麻酔になる。術後目が覚めなかったら、どうしようと時々不安になる。家内は気楽に語りかける。
「頻尿がおさまるんだから、いいんじゃない」
「手術を受けるのは、オレだぞ。心配じゃないのか」とむっとしたら
「今の医学はすすんでいるから、元気に退院できるわよ!」
背中をポンポンと軽く叩かれる。(仕方ない。頑張るしかないか)(今年も一発屋作家と云われないよう頑張ろうか)
ライ麦畑で遊ぶ子供たちが落っこちそうになると、サッと出て行って抱きしめる私の仕事。サリンジャーの本に遊びに出かけるとしよう。(2024年3月)
著作品一覧
アムステルダムの詭計(2016年4月 原書房)


